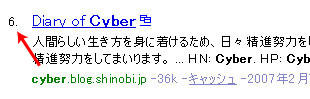私は、ただの非力な人間だ。
どんなに頑強な肉体の持ち主でも、どんなに強靭な精神の持ち主でも、人が人である限り、自然の力には逆らうことが出来ず、平伏す時がある。助けを求める人がすぐそこに、目の前にいるのに、自分は何も出来ない。波にもまれ、苦しみ悶え、絶命していく様を、ただ見ているだけ。
『今まで200人以上救った大記録保持者』?
そんな数字など、私の前には何の意味も無い。
私は救難士だ。救難士でありながら、たった200人『しか』救えなかったのだ。
ただの、タフで熱い心を持つ救難士の活動録ではない、その裏に見え隠れする苦悩やジレンマを描いているハートフルな人間ドラマです。
ベテラン救難士と、救難士を目指す青年。どちらも、死に直面する苦しい経験を刻んでいる。
同時に、「守るべきものを守れなかった」ことに対する苦悩も。
「もし、あの時自分がもっと力を持つことが出来ていたら」 。
そんな願いを誰よりも強く持っていたとしても、もう二度と時間は戻らない。失われた生命は、戻ってこない。無愛想に部下達を指導しても、虚しいまでに自分の記録を誇示しても、目に焼きついているのは、耳にこびりついているのは、自らの非力に対する自責と後悔。
だから、今日も彼らは誰かを救い続けている。まるで、神へ懺悔するかのように。
「自分が救うことができることなど、ほんの一握りしかいない」
勿論これは、単なる卑屈な言葉ではなく、現実の言葉です。実際、僕自身も「人間やれば何でもできる」と思っている人間ではありません。別に、そう考えることが悪いわけではありませんが、その考えがやがて自分の中に傲慢さを芽生えさせたくないからです。
自分が非力なのが分かっているから、一握りの人しか守れないのが分かっているから、せめて、目の前にいる人は、全力を以って守りたい。そして、その自分に絶対に満足しない。自分が死ぬまでに守れる人間が、それでも一握りであったとしても、一人、また一人と、手を差し伸べられる人を増やしていきたい。
孤高で、ストイックで、そして誰よりも熱のこもった救難士の物語。
どんなに苦しい過去を背負っていても、救うべき生命がそこにあれば、彼らは必ずかけつけます。
時間は、生命は、待ってくれないから。
このブログのアクセス履歴を調べてみたところ、Yahoo! Japanから『Cyber』というキーワードでいらっしゃった方がちらほら。
ためしに、Yahoo! Japanで『Cyber』と入力してみたところ、↓
『Cyber』という単語自体、割りと多く使われていますし、こんなアホな文章垂れ流しているだけのサイトにも関わらず、アクセスしてくださるのは、非常に有難いと思っていますが……
根が貧乏性なだけに、若干疑心暗鬼になっているのであります(汗)。
ちなみに、Googleで『Cyber』で検索してみたところ、いつまでたっても僕のサイトは、表題すら現れませんでした。まぁ、本来ならばそんなもんだよね…… orz
きっと、Yahoo! Japanの上位ランクインも、一過性のものでしょう(この記事が公開された瞬間、他のサイトにアクセスが集中して、瞬く間にこのサイトが1000位くらいに転落するかも……(汗))。
これも一つの励みになりますので、これからも細々と隙間産業的にやっていこうと思います。

。
しかし、彼が立ち向かわなくてはならないものは、10万の敵だけではなかった。そして、彼にとって人間とは、たとえ敵であろうとも傷つける対象ではなく、守り通す対象なのだ。
時代物アクションの中国映画でよく見られる、上映初期から覚えきれないほどの登場人物とその相関関係。それに対しあまりにアンバランスな、シンプルすぎる物語。あまりにもあっさりしすぎる物語の展開が中盤にまで及び、映画というエンターテインメントとして成り立っているのか、と不安に思ったが、後半でその考えが露に消えた。
シンプルな物語構成であるからこそ、伝えたいメッセージを前面に出そう。そういった意気込みが感じられたからだ。それは、主人公の一挙一投足にも込められている。
それは、人間誰しもが持ち得る、光と影。
誠実と誠意。欲望と陰謀。
方や自らの知恵と身体を投げ出し、たとえ敵でも一人でも死者を出さぬよう奮闘する。
方や己の保身と利権に溺れ、救世主に対してでも平気で仇を為す。
こういった類の物語は、過去にも数限りなくある。ただ、この作品は物語り構成がシンプルであるだけに、そのメッセージは強烈に残る。その余韻は、今でもだ。
この作品は、原作であるコミック『墨攻』を映画化したものだという。僕は原作を読んだことは無い。原作もこの映画と同様、墨家の理念から『反戦』や『非攻』といったメッセージを謳い文句にしていたと考えるが、その根本となるのは、人間の精神活動だ。それを如何に制御し、そして行動に移せるか。それは、今もって尚、一人一人の人間に問われる課題である。
墨家の考え方や理念は、僕自身もそうだが、人間一人一人が見習い、考えるべきではないか。
勿論、これは至極当然のことだ。だが、当然のこそだからこそ、見落としやすいし、忘れやすい。
今、社会で多大に騒がれている数々の事件が、それを反映しているかのように。
彼らは本当に実在していたのか、それは定かではない。
でも、伝説であろうとも幻であろうとも、彼らの考え方や理念は今でも生きている。
この作品を通しでなくても、彼らの考え方や理念に、触れてほしい。人間の根源として大切なものは何なのかが、きっと見えてくるはずである。

ホームレスになるほどのどん底に陥ったものの、自らの望みを諦めず這い上がった、実在する男のサクセス・ストーリー。
アメリカン・ドリームを象徴する物語、と言われているこの作品です。が、確かに主人公の奮闘振りには目を見張るものがありますし、最後についに夢を掴んだ瞬間は、「ああ、本当によかった」と思うけれど、「この作品が好きですか?」と問われると、「う~ん…」と首を傾げてしまうのが正直なところ。
なぜかというと、端から見れば、主人公は途轍もなく意地っ張りで頑固で、時には身勝手であるから。妻も子供も、生活する場を維持していく身であるにもかかわらず。同じアメリカン・ドリームとしての作品であるならば、ジム・モリスの半生を描く『オールド・ルーキー』の方が僕は好きです。
けれど、そんな彼に対しても、見習わなくてはならないところがあって。それは、『一切妥協を許さないところ』。そして、『何が何でも、しがみ付いてでも守り通すこと』。
サバサバした性格の人間であれば、もし夢を、自分の望みを追い続けるならば、それ以外のものを切ってしまうと思うんです。自分の家族とか。その姿勢に家族が薄々でも感付いてしまうと、「貴方の負担になるなら別れましょう」といって離別してしまう。この作品の主人公の彼は、奥さんとは別れてしまうけれど、本当はしがみ付いてでも手元に置いておきたかったんじゃないんでしょうか。でも、自分の気位や自尊心の高さが、その気持ちをはねつけてしまい、「出て行くなら出て行け」と言ってしまう。それでも、最愛の息子は手元に置いておきたい。
自分の夢は叶えたい。愛する人も守りたい。手に入れたものはもう誰にも奪わせない。触れることすら許さない。むさ苦しいほどの情熱を持ち続けていても、ここまでの覚悟はそう簡単に持つことは出来ないでしょう。
でも、それは同時に家族を苦しめてしまうことにもなります。それでも夢を、幸せを追求していくのであれば、よほどの家族の理解が得られないといけません。
そういった意味では、この作品は主演のウィル・スミスは勿論のこと、彼の実子であり、主人公の一人息子を演じたジェイデン・クリストファー・サイア・スミスに拍手を送りたいです。
本来なら、色んなことをスポンジのように吸収していく5歳という年頃であれば、各地を転々とし、父親の苦渋に満ちた顔を見れば、きっと泣き叫びたいはず。それでも彼は決して泣かなかった。唯一、お気に入りのおもちゃを落としてしまった時、一筋の涙をこぼしてしまったけれど。
人間はプライドを持たなくてはならないけれど、誰かを苦しめるようなプライドであれば、必要ありません。それは僕の考えです。
でも、誰かを苦しめると分かっていても、そのプライドだけは捨てられないというのであれば、しがみ付いてでも守りなさい。この考えは、きっと日本人にはあまり馴染まない考え方なのかもしれません。僕自身も何かしらの願いやプライドを持っていますが、守らなければならないものが目の前にあると、その願いもプライドも、霞んでしまうかもしれません(多分これが、冒頭の質問に対する答えの源泉)。
が、その考えを持っている人に対してであれば、きっと、この映画は心に響く作品になるのでしょう。
 この映画のポイントは、『退屈』と『窮屈』。
この映画のポイントは、『退屈』と『窮屈』。政略結婚によって少女が嫁いだ先は、それまでの少女の日常から見ればあまりにもバカらしく、考えられないものばかり。目の前に陳列される日常品は、どれも一流の美術館に出してもおかしくないような、眩いものばかり。でも、彼女の目には、それらはくすんで見える。煌びやかな装飾品も、どこか灰色じみた感じがする。
観客は、そんな心情の少女の『目』に映し出された光景が、スクリーンに映し出されます。家具も、ドレスも、食べ物も、どれもこれも輝いて満ち足りているのに、少女の目には、ちっとも輝いているように見えない。どこに行っても人だらけ。人人人。皆傅いているのに。ちっとも満ち足りない。
そんな少女に、更に追い討ちをかけるのが、世継ぎ問題。
異国の地に、たった一人。嫁いだ瞬間から、次代の世継を産まなければならないことが宿命づけられている。一日、また一日、伴侶との間に何も無ければ、周囲から浴びせられる冷たい視線と罵詈雑言が激しさを増す。少女の身と心は、すっかりボロボロに朽ち果ててしまった。
そんな少女の目に飛び込む光景が、唯一『本当』にカラフルに輝くのは、友人達と朝まで遊んだり、演劇に興じたり。でもそれは、まるでシンデレラのように魔法がかけられている限られた時間の中でのみ。魔法が解ければ、また『退屈』で『窮屈』な生活に戻るだけ
18世紀に実在し、歴史に名を残す有名な少女の物語。これが、少女と彼女を取り巻く人物の史実に合っているかどうか、また、彼女が本当にそういう心情にあったかどうかは別。実在した人物と史実を元に作られた、オリジナルの物語、として観るといいかもしれません。
少女であれば誰しも、「お姫様に生まれたい」「お姫様の生活をしたい」と憧憬を抱くものですが、本当にお姫様になった時のその生活ぶりといったら。彼女のことを、一人の『人間』として扱われていたのではなく、世継を身篭るための『器』とでしか、当時のヴェルサイユの人々は見ていなかったんでしょうね。
映し出される映像の数々は、正に『退屈』と『窮屈』をそのまま表現しているかのようでした。映画作品として、あまりにも駄作で『退屈』と思えるものは数あれど、意図的に『退屈』を映し出す映画は、ほとんど無いのではないのでしょうか?
まるで、観客がこの作品の主人公である少女と『同じ』目線で観てもらいたいがための作品になっていると感じました。
この作品は、ご覧になる方々の感受性に左右されるのは確かです。勿論、「終始退屈だった」と思われればそれまでですし、それを批判する資格など僕にはありません。が、この少女が実在していたにしろしていなかったにしろ、どれだけの苦痛と屈辱を味わっていたのか、それを汲み取ってご覧いただければと思います。