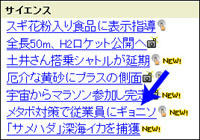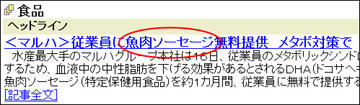この映画を観ている最中、僕は思った。
この映画を観ている最中、僕は思った。「今まで、何百何千、数多と報道されてきた世界のニュース。そのうち、一体どれだけのものに関心を持っていたのだろう?」
2割? 3割? いや、違う。きっと、1割どころか、1%にも達していないだろう。そして、これは報道された中のニュースに限ったことである。報道されないニュースも含めれば、僕がこれまでに関心を寄せたニュースなんて、ほんの一握りだ。
勿論、関心を寄せたところで、何ができるわけではない。一個人の持てる力など、たかだか知れている。全ての問題を解決しようなんておこがましい事は考えていない。でも、「関心を寄せている」と「寄せていない」とでは、大きく異なる。何をするわけでもない。ただ関心を寄せるだけ。それでも、その問題に対する姿勢や考え方は違ってくる。徐々に行動に移そうと考えてくる。結果として、自分の行動がその一端しか担うに過ぎないとしても。
僕は思った。そして打ちのめされた。
如何に、自分が多くの問題に関心を寄せていなかったか。目をそらしていたか。他人事のように考えていたか。
神が傲慢な人間から奪ったのは、何も共通の言葉だけではなかった。そして共通の言葉を奪うことが、神が人間に与えた罰ではなかった。『無関心』。これが、神が人間に与えた最も重い罰。
モロッコにおいて発生した銃撃事件。撃たれたのは、観光中のアメリカ人夫婦。
観光中、アメリカに子供たちを預けた家政婦は、不法就労のメキシコ人。
銃撃事件で使用されたライフルの登録上の所有権は、日本人の会社員。
全ては、独立の事象。繋がっているのは、銃撃事件だけ。それぞれの国のそれぞれの事象に、接点はおろか、関連性すらどこにもない。
しかし、銃撃事件は、単に無関係の事象を繋げるための材料に過ぎない。この映画で表現したかったのは、それぞれの事象の中に介在する、人間が人間であるが故に犯す『過ち』と、それに対する『関心』であると、僕は考える。ひとつの『きっかけ』が、世界中に存在する様々な問題を浮き彫りにさせ、それぞれに関心を寄せることが、この映画の狙いではないだろうか。
その対照的なシーンとして僕が印象に残っているのは、モロッコでの銃撃事件を、日本のニュースで報道されているシーン。中盤で、菊池凛子が扮するチエコが、自宅のリビングで寝そべりながら、ラストの方で、二階堂智が扮するケンジが、酒を飲みながらニュースを見るシーンがある。でも、両者とも、「自分には関係ない、地球の裏側で起こった事件なんて」という目をしている。
勿論それは、地球の裏側で生活する人々にも同じこと。不法就労問題も、未成年の飲酒や危険な遊びの問題も、「自分には関係ない」と思っている。だって、自分たちの生活圏の中で銃撃事件が発生して、重傷者が出たのに、誰も手を差し伸べようとしないから。ただ見てるだけ。巻き込まれるのが怖いから。
確かに、一つ事件をきっかけに繋がる全ての事象を垣間見るのは難しい。しかし、どこかに必ず『因果』があり、『繋がり』がある。たとえ当事者が意識していなくても、見えない『繋がり』が存在するのだ。
重要なのは、僕たちがその繋がりの奥にある事象に、どれだけの関心を抱くか。更に、それらに対して自分に何が出来るか。全てを何とかしようなんて考えない。一人で何とかしようなんて考えない。身近なところであろうと、気の遠くなる距離と時間の関係であろうと、多くの人が、様々な『問題』や『過ち』に対し、関心を抱こうとすることを願わずにはいられない。
勿論、それは僕自身に対しても言えることなのだ。
 人が人を殺す。そんなことを仕出かせば、大抵の人間は動揺を隠せません。勿論、殺人を積み重ねていけば、それが『日常』になり、動揺も次第に無くなっていきます。『殺人』という『異常行動』が、『日常』になっていけばいくほど。
人が人を殺す。そんなことを仕出かせば、大抵の人間は動揺を隠せません。勿論、殺人を積み重ねていけば、それが『日常』になり、動揺も次第に無くなっていきます。『殺人』という『異常行動』が、『日常』になっていけばいくほど。だが。彼は違った。彼は最初の殺人から、動揺を一切見せなかった。自分が刈り取った他人の生命は、彼にとってはただのモノ。いや、彼の欲求を満たすための芸術品。のちに引き起こされる数々の忌まわしい殺人事件は、そんな彼の常軌を逸した欲求から生まれ出ます。
人を死に追いやるたびに、人の死に顔を愛でるたびに見せる、恍惚にも似た笑み。その原動力は、幼い頃に植えつけられた、筆舌しがたい恐怖体験。
この作品は、ハンニバル・レクターの中に眠る狂気の序曲。『死』に『美』を求める、究極とも呼べる悪夢の始まり。
もしこれが、『羊たちの沈黙』や『ハンニバル』とは別の物語として位置づけている、単体の作品あれば、それはそれで面白いと思います。
主人公であるハンニバル・レクターの青年期を演じた、ギャスパー・ウリエル。人を死に追いやる直前に見せる、頬まで引き裂かれているような悪魔を彷彿させる笑み。これから先々で繰り返される悪夢のような所業を行う者としての表情としては、観ているこちらとしても身震いしてしまうほど。ただ、どれだけ彼が『ハンニバル・レクター』としてのキャラクターに扮そうとしても、この作品の『ハンニバル・レクター』の数々の所業は、その後の彼の行動を描いている『レッド・ドラゴン』『羊たちの沈黙』『ハンニバル』に繋がるような気配がありません。
最愛の妹を虐殺され、さらにその虐殺が、自身にも決して逃れることの出来ない、そして筆舌しがたい恥辱を強いられてしまう。
その時、彼が後の『ハンニバル・レクター』としての魔性に目覚めたのか、それとも、最愛の妹を虐殺した者達を次々と殺していく最中に、魔性に目覚めたのか。その点が曖昧な気がします。
例えば、『007/カジノ・ロワイヤル』では、愛した女の突如とした裏切りで、人に対する信頼の一切を絶ち、いままでやんちゃ坊主のようだった『ジェームズ・ボンド』が、冷酷なまでの暗殺者になった。単純に見えながらも、その変容振りには目を見張るものがありました。しかし、『ハンニバル・ライジング』における彼の殺人は、全て復讐心からなるものばかり。とても、後のアンソニー・ホプキンスが魅せる『ハンニバル・レクター』からは遠いと思うのです。
けれど、一旦離れて考えてみると、こうも思ったりします。
最愛の妹の虐殺以上に、虐殺を契機に犯人達がハンニバルに向けられた最も残酷極まりない行いが、彼の中の狂気を目覚めさせた。
彼にとって犯人達を殺すことは、ただの復讐にすぎなかった。でも、一人、また一人と殺し、妹を手にかけた彼等の血を、肉塊を見て行く内に、自分の中の狂気が徐々に目覚めていく。最初はそれを否定した。だってもしそれを受け入れてしまえば、自身もまた彼等と『同じ』になってしまうから。
でも、人殺しを繰り返せば繰り返すほど、その『本性』は次第に顕在化していく。最初は、復讐に見せるただの一面―『二重人格』のようなもの―であったものが、次第にその『本性』が『彼自身』と同一化していく。「これはただの復讐」「やつらとは違う」と呪詛のように自分自身に対して唱えながらも、もう自分で自分を止めることができない。制することができない。
そしてついに、封印したかった記憶を、犯人達に無理矢理引きずり出され、否応なく自分の『行い』を自覚させられたことで、彼と彼の『本性』が一体化する。それこそが、殺人鬼『ハンニバル・レクター』の誕生の瞬間。狂気と悪夢の始まり。
まぁこれは、単に僕の想像に過ぎませんが、その潜在的な『本性』が徐々に顕在化していくような描写があれば、「ただの復讐?」「本性の目覚め?」の曖昧なラインも、一つの物語の要素として楽しめたかもしれません。
でも、後々のハンニバル・レクターシリーズを念頭に入れなくても、『ハンニバル・ライジング』を単体の作品として、鑑賞することは出来ると思います。勿論、『それなり』の映像は出てきますので、ご覧になる方は、相応の覚悟が必要です。
『春の花』と一括りに言っても、その種類や咲く時期は色々あります。
まだ厳しい寒さが残る時期に咲き始める梅。春の爛漫とした空気の中で、燦然と輝くように咲き乱れる桜。暖かな陽気に包まれながら咲き始めるチューリップ。新緑が芽吹き、夏の気配がすぐそこまで来ている時が見頃の菖蒲。
大いなる自然の力に身を任せながら花を咲かせる上では、それらを一度の時期にいっぺんに見るのは非常に難しい。でも、やはり少しでも多くの色と種類の花を愛でたいもの。それには、この春に咲く種類の花を、一度に沢山見ることが出来る境界線となる時期である、4月中旬の時期が一番適しているのではないかと思います。
遅咲き・早咲きのタイミングもありますので、運がよければ、思っていた以上の花を愛でることが出来るかもしれません。4月の中旬であれば、もう桜は散ってしまい、新緑で覆われている頃ですが、ちょっと目覚めが遅い桜の花をポツポツと見ることが出来ますし、逆に、気の早い5月に咲く花を見ることが出来るかもしれません。




国営昭和記念公園では、正にそれを実現するほどの種類の色とりどりの花が咲き乱れています。ちょっと遅めですが、でも菜の花はまだ一面の黄色い絨毯を作り上げているし、個性豊かなチューリップの花も、まるで自身を誇示しているかのように、競い合っているかのように咲いておりました。
こういうところを、花を愛でながら歩いていると、福山正治の『東京にもあったんだ』を自然と口ずさんでしまいます。都心から電車で1時間足らずのところでも、こんな綺麗な場所があったなんて。
東京に住み始めてから2年半。でも中学・高校が東京だったし、大学は神奈川だけど決して東京は無縁の場所ではない。
でも、まだまだ知らない。これから知るところは増えるけれど、知らないところもまた増えるでしょう。だからこそ、面白い。
「東京にもあったんだ、こんなキレイな場所が」。
『東京都』の写真集についてはこちら
?? ギ ョ ニ ソ ??
新しい薬品か何かかな?
と思い、クリックした先の記事を見たところ↓
ははぁ。『魚肉ソーセージ』を略して『ギョニソ』……
って略しすぎじゃボケッ!
その昔、新聞のテレビ欄で、ドラゴンボールの再放送を『ドラゴン[再]』って書かれるくらい訳の分からない略し方をされた一例でした。
このくらいのネタしかないので。
はふっ、疲れた……
 人間の生命に比べたら、ダイヤモンドの価値など『たかが』である。
人間の生命に比べたら、ダイヤモンドの価値など『たかが』である。だが、その『たかが』のために、今も尚、多くの人間の生命が奪われている
『高価なものの覇権争い』は、今に始まったことではない。
コーヒー、紅茶、胡椒。何十年何百年と繰り広げられる、人間の独占欲から生まれる闘争は、枚挙に暇がない。そして、その闘争の裏には、必ず存在する『弱者』。虐げられ、強奪され、更には人間の人間たる尊厳まで粉々にされて。彼等の『生命』はおろか、『幸せになる権利』さえ、『たかが』の前には塵芥と化す。
この先、世界は、『平等』になることなど、あり得るのだろうか
目の前に飛び込んでくる映像は、そのほとんどが「何だこれは」。「こんなことが、実際にあっていいのか」。そんなふうに思える作品です。
『ナイロビの蜂』のように、『ブラッド・ダイヤモンド』がフィクションであろうとノンフィクションであろうと、そんなことはどうでもいい。これと同じような紛争が、10年前のシエラレオネ共和国で、実際に起こったのですから。
今は平和になっていると聞きます。でも、本当に? まだ何十万人という少年兵が、「人を殺すこと」がどういうことなのか、まるで分かっていない少年兵が数多くいる中で、本当に平和になっているのだろうか? きっとまだ、内戦の火種は今も尚くすぶり続けている。貴重な資源が眠る地で、虎視眈々と狙う者たちの汚れきった視線に弄ばれながら。
年端も行かない少年達。その手に銃を構えながら笑っている。
そして、笑いながら人を殺す。
『人殺し』という罪と、それを犯したことによる罰が、どんなことかも知らないまま。
「国民のため」に、国民を「殺す」。笑いながら、その手を血に染める。
地球の裏側では、これが『日常茶飯事』として繰り返される。今日も、明日も、その次の日も。
何が『善』とか、何が『悪』とか、もはやそんな言葉では陳腐すぎて言い表せない、そんな残酷さがこの作品から漂っています。
この作品の真実がどうあれ、それでも、今でも尚虐げられる人は数多く存在し、何百万人もの難民が溢れていることは事実。神の声が届かない地だからこそ、救えるのは、同じ血の通う同じ『人間』しかいない、ということを、改めて痛感しました。
是非、映画館へ足を運んでご覧下さい。
「世界を見る目が変わる」。いや、むしろ「世界を変える」ためには、「世界を見る目を変える」くらいの勢いが必要なんじゃないかと思うくらいです。虐げられた人々にとって、本当に『幸せ』な日々を取り戻すために。